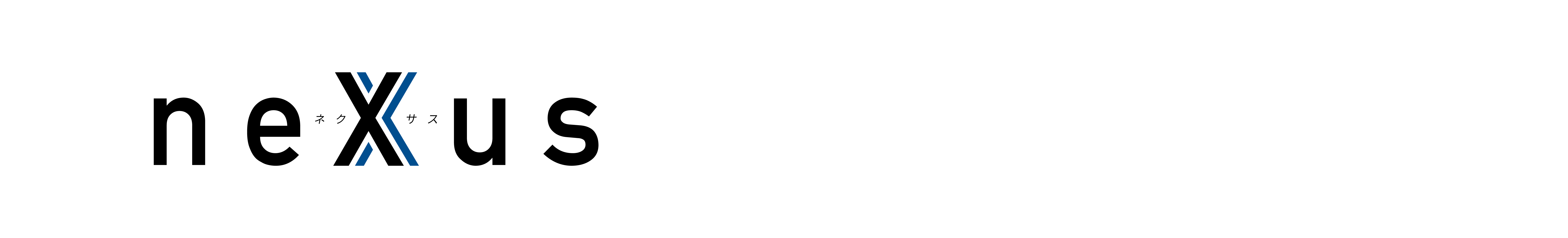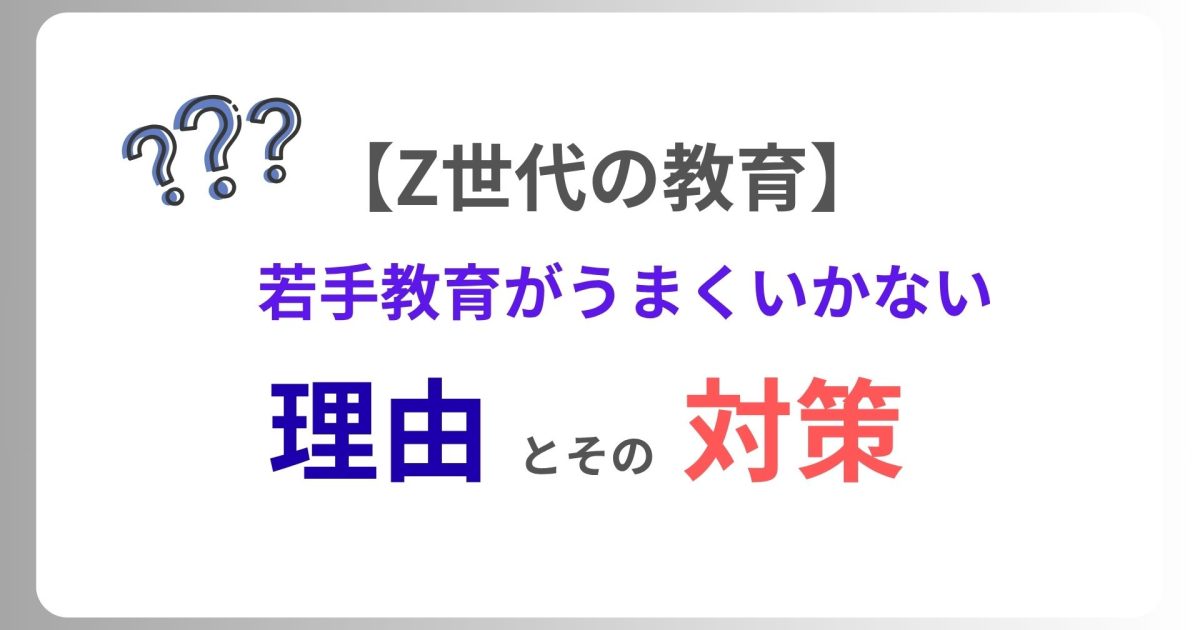新卒社員が入社して3か月が経過する6月末。このタイミングで「思ったように育たない」「コミュニケーションが難しい」と感じている経営者や採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
Z世代は、主に90年代終盤~12年頃の生まれと言われています。
インターネットやSNSが身近な環境下で育ったZ世代は「ソーシャルネイティブ」とも言われており、価値観も多様化。特徴を掴んだうえでこれまでとは違ったアプローチが必要と言われています。
本記事では、現代の若手社員、特にZ世代の特徴を踏まえた教育の課題と対策を、現場の事例をもとにご紹介します。

目次
若手教育における主要な課題
若手教育の見直しが必要とされる背景には、以下のような課題があります。
・育成目的が曖昧
・経営戦略との連動不足
・挑戦を促す制度や文化の未整備など
これらの課題を解消し、効果的な若手教育を実現するためには、まず相手を正しく理解することが出発点です。特に現在の新入社員の多くを占める“Z世代”は、これまでの世代とは異なる価値観や働き方へのニーズを持っています。
その違いを知らずに従来の育成方法を押しつければ、せっかくの人材も活躍の場を見いだせずに離れてしまうかもしれません。
では、Z世代はどのような特徴を持ち、どのような関わり方が効果的なのでしょうか。次に、Z世代の傾向と、それに合わせた育成のポイントについてまとめております。
Z世代の特徴と育成のポイント
Z世代の特徴として大きくあるのが、「働くことに不安を感じる」「無理のない範囲で成長したい」という声です。
JMAMが新入社員を対象にインターネット調査をした結果では、
無理のない成長と働く場所の自由度を求めるZ世代が多くを占めています。
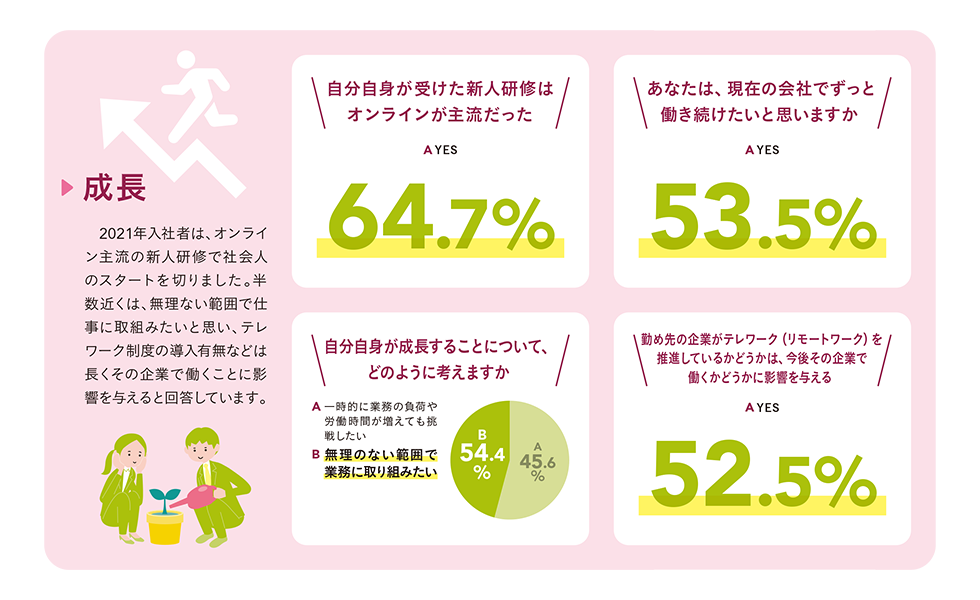
https://www.jmam.co.jp/hrm/column/0062-imadoki2021.htmlより
指示や注意だけをするのではなく、安心して働けるような関わり方が必要になってきます。
Z世代の価値観を理解することが育成の出発点
Z世代はワークライフバランスやフラットな関係性を大切にし、「納得して働けるか」を重視する傾向があります。上からの指示に従うだけの働き方では力を発揮しづらく、対話を通じて目的を共有する姿勢が求められます。

安心と信頼を基盤にした関係性の構築
TAKAYAMAでは「絶対に怒らない」育成方針を徹底しています。Z世代にとって、安心できる環境は行動の原動力です。ミスを責めるのではなく、成長の糧と捉えて一緒に考える姿勢が信頼を生みます。
具体性のある指導と、背景説明の重要性
指示を出す際には「なぜこの業務が必要か」「誰の役に立つのか」といった背景を伝えることで、Z世代は主体的に動きやすくなります。ただ“やり方”を教えるのではなく、“意味”まで伝えることがカギです。
効果的な育成施策の事例
デジタルツールを活用した日常的なフォロー
テレワークやフレックス制度などが当たり前になった今、若手との距離感をどう埋めるかは多くの企業の課題となっています。TAKAYAMAでは、Microsoft Teamsを活用して日常的な“ちょっとした声かけ”を継続して行う文化が根づいています。特に、緊急でない「報・連・相」をあえて受け入れることで、若手にとって相談しやすい空気をつくり、信頼関係の土台となっています。
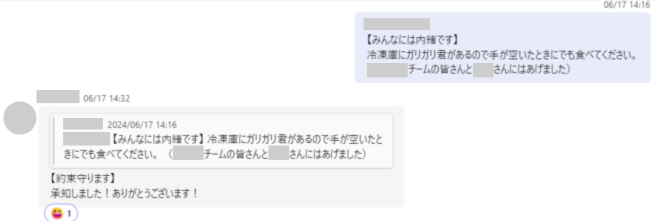
成長実感を可視化する仕組みの導入
育成において重要なのは、「自分は成長している」と感じられる仕組みを持つことです。TAKAYAMAでは、入社1か月目からお客様対応や会社案内などを練習し実践することで、目に見える成長を実感するきっかけになっています。

ブログ形式での振り返りと内省の促進
その日の学びや気づきをアウトプットさせています。学んだことや反省することなど、内省力が高まるだけでなく、チーム内の共有や共感にもつながり、育成の相乗効果を生んでいます。
若手教育の再構築に向けて
採用段階から「育てやすい人材」を見極める
Z世代の育成を成功させるためには、「誰を採るか」も重要です。TAKAYAMAではOfferBoxを活用し、自社と価値観の合う学生にピンポイントでアプローチしています。これは、自社に合った価値観や志向を持った人材に出会うための有効なアプローチです。
採用から育成までを一貫した“人材戦略”として設計する
採用と育成は切り離すものではなく、ひとつながりのプロセスです。採用段階から価値観のマッチ度を重視し、入社後の育成方針とリンクさせることが、定着率や活躍度の向上に直結します。
教育を「業務の一部」に位置づけ、継続的に改善する
育成を“特別な活動”として捉えるのではなく、日常業務に組み込むことが重要です。PDCAを回し続けることで、属人化を防ぎ、組織全体の育成力を底上げすることができます。
このように、若手教育は「教えるスキル」だけでなく、「組織全体の育成力」をどう設計し続けるかが問われるフェーズに入ってきています。
次の一手は、「育成できる仕組み」の構築です。
Z世代の教育・育成には、一人ひとりに寄り添う姿勢と同時に、それを支える「仕組み」が不可欠です。育てる人材だけでなく、育てる体制そのものを整えることが、若手の定着・活躍につながる第一歩です。
もし「何から始めていいか分からない」「社内で取り組んでみたがうまくいかない」と感じている方には、仕組みから設計する“Webセンニン”の支援が力になります。

Webセンニンは、貴社の状況や育成課題に応じて、DX・人材育成・情報共有の仕組みを一緒につくる伴走型サービスです。
「人が育つ会社にしたい」と本気で考える経営者・採用担当の方は、まずはお気軽にご相談ください。